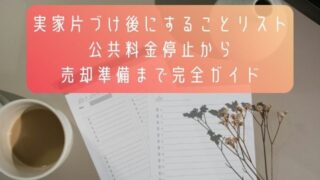空き家になった実家どうする?|遠距離から売却を決めた3つの理由と進め方

実家が空き家になったとき、「売る?残す?」と迷う人は多いと思います。
私たち姉妹は遠距離に住んでいて、実家に戻る予定はなし。
そんな状況で、迷わず売却を決めました。
この記事では、なぜ迷わなかったのか、どう家族で話し合ったのか、そして決断までのステップをまとめています。
同じように実家をどうするか悩んでいる方のヒントになれば嬉しいです。

実家を売ると決めた理由
実家が空き家になったら、私と妹はあまり迷わず「売ろう」と決めていました。
というのも、私たち姉妹はそれぞれ遠方に家族と暮らしており、実家に戻る予定はまったくなかったからです。
「もし親がひとりになったら、どちらかの家に来てもらって一緒に暮らそう」
──そんな話を以前からしていて、実家はその時点で手放すつもりでいました。
迷わなかった3つの理由
遠距離からの管理が難しい
空き家になると、郵便物の確認、草取り、換気など定期的な管理が必要です。
遠方から通うのは現実的ではありませんでした。
維持コストとリスクがかかる
固定資産税、光熱費、火災保険の維持だけでなく、空き家は防犯や老朽化のリスクも高まります。
「空き家問題」という言葉もあるくらい、放置するのは避けたいと考えました。
親もこだわりがなかった
親自身も「もう住まない家だから好きにしていいよ」と言ってくれていたため、売却への心理的ハードルが低かったです。
家族会議は“確認作業”として
迷いは少なかったとはいえ、いちど姉妹と親で会った時に下記のことを確認しました。
- 本当に売却していいか
- 仏壇や思い出の品をどうするか
- 不用品の処分と家の片づけの段取り
決定というより、「これでいいよね?」と最終チェックをする感覚でした。
結論
結果的に、迷わずに売却を決めたことで、空き家をどうするか悩む時間を減らし、次のステップ(片づけ・査定・契約)に集中できました。
同じように遠距離に住む方で、実家をどうするか悩んでいるなら、「将来的に住むか住まないか」を先に決めるだけでも心が軽くなると思います。
実家を売るかどうか、迷うときのすすめ方
そうはいっても、そうそうスムーズにいかない場合も多いですよね。
兄弟姉妹、親戚が多かったり、遠方に暮らしていたり、親自身が反対もしくは迷っていたりするとなおさらです。
そんな場合でも、下記の手順ですすめてみてください。
後回しにすればするほど、物事が停滞したりトラブルが出たりしがちです。
我が家の場合、親の認知機能の低下、緊急入院、実家の害獣被害など、思ってもみなかったことが次々と起こりました。。
すすめ方
- 迷っている、反対されている
↓ - 考える(状況把握、メリットデメリットなど)
↓ - 話す(まずは誰かひとりでも話しやすい家族に)
↓ - 調べる(情報収集)
↓ - 動き出す
まずは状況と気持ちの整理
- 「本当に売っていいのか」「親の気持ちは?」という不安を書き出す
- 実家を残す/売る、それぞれのメリット・デメリットを書き出す
- 「後悔しない選択」を意識する
先にも述べましたが、私たち姉妹の場合「売るかどうか」でそこまで悩みませんでした。
遠距離に住んでいて、実家に戻る予定もなし。
親がいずれどちらかの家に来て暮らす想定もしていたので、実家は「いずれ売る」と決めていました。
我が家の場合
- 私たち姉妹は遠距離住みで実家に戻る予定がない
- 実家は築年数が経っており、修繕や管理が負担になる
- 親が施設入所して実家が空き家になったという条件を一つずつ紙に書き出したことで、「売る方向でいいよね」と気持ちが整理できました。
それでも、一度紙に書き出して整理したのは良かったです。
「戻る予定なし」「維持費がかかる」「空き家管理は大変」といった条件を書いてみると、気持ちがスッキリしました。
まずは残すメリットとデメリットを整理してみると方向性が見えやすいと思います。
残すメリットとデメリット
残すメリット
- 帰省先として使える
お盆や年末年始、親戚が集まる場として残せる - 思い出の場所を守れる
子ども時代の記憶が残る場所として心の拠り所になる - 資産として保有できる
土地価格が上がる可能性もある - 貸すことができる
賃貸にして収益化できる(ただしリフォーム費用はかかる) - 相続の選択肢を残せる
兄弟姉妹で将来的に使い道を相談する余地がある - 将来、子や孫が使える可能性がある
残すデメリット
- 維持管理の手間がかかる
草刈り、換気、郵便物の確認、害獣対策などを定期的にする必要がある - 固定資産税や光熱費がかかり続ける
誰も住んでいなくても年間数万円〜十数万円の維持費が発生 - 防犯や劣化リスク
空き家は泥棒や放火のリスクが高く、老朽化も早い - 遠距離だと対応が大変
トラブル時や管理のために頻繁に通えないと精神的負担になる - 相続時に揉める可能性がある
売る/残すで兄弟の意見が割れると大きな問題に
このようにメリットもあるけれど、実際には「誰が管理するか」「どれくらいコストを負担するか」が大きな分かれ目になります。
私たち姉妹の場合は、遠距離で管理できる自信がなかったのと、維持費をかけ続ける理由もなかったので、迷わず売却を選びました。
家族と話し合う
次に、家族全員で意見をそろえることが大切です。
特に親の気持ちを無視して一方的に決めてしまうと、後から「やっぱり売りたくなかった」とトラブルになることも。。
- 親や兄弟姉妹と時間をとって話し合う
- 遠距離ならオンライン会議やグループLINEも活用
- 話し合った内容をメモ・記録して残すと後で揉めない
私たち姉妹は、母に認知症の症状が出始めた頃に、実家をどうするかを話していて、二人とも実家に戻る予定は無いことを確認していましたが、両親とは具体的に話してはいませんでした。(タイミングがなかなか難しい。。)
けれど、両親が施設入所を決めたタイミングで、「じゃあ実家どうする?」と自然に話題にしました。
両親も「誰も住まないなら売るしかないね」とあっさり賛成でした。
(害獣被害が深刻化していたことも大きかったと思います)
兄弟姉妹間の意見もLINEでやり取りを残しておいたので、後からトラブルになることもありませんでした。
ここは重要ポイントで、きちんと話し合いの記録を残すと後々安心です。
売却に向けた情報を集める
実際に売るかどうか決める前に、情報を集めると現実的な判断ができます。
- 売却にかかる費用(仲介手数料、解体費、固定資産税)を調べる
→仲介手数料の目安(売却価格×3%+6万円+税)
→解体費用の相場(木造なら坪3〜5万円) - 売却以外の選択肢(賃貸、空き家管理サービス)も調べる
- 近隣の売却価格相場を知る(ポータルサイト、簡易査定)
→SUUMOやアットホームなどで調べる
迷いが少なかったとはいえ、動く前に相場感は調べました。
近隣の売却価格をポータルサイトでチェックし、不動産会社に簡易査定を依頼。
仲介手数料や売却までの流れもざっと把握しておいたことで、手続きがスムーズでした。
もし迷っている方は、「売る」「貸す」「管理サービスを頼む」など選択肢を並べて比較すると現実的に判断できます。
動き出すタイミングを決める
迷っていると、あっという間に数年たってしまうこともあります。
親の体調や介護の状況、空き家の傷み具合などを見ながら、動き出す時期を決めるとスムーズです。
- 親が元気なうちか、介護や入院をきっかけにするか
- 売却準備にどれくらい時間がかかるか逆算して計画
我が家では、父の入院と母の施設入所が重なったタイミングで「今だ」と決意しました。
家が完全に空いてから片づけ〜売却準備まで一気に進められたので、結果的に効率が良かったです。
迷いが少ない方ほど、タイミングを逃さずサッと動くと効率がいいです。
- 迷いが少ない場合でも「条件整理→家族合意→情報収集→タイミング決定」の流れは踏んでおくとスムーズ
- 記録を残す&最低限の相場チェックは必須
- 動き出すタイミングを逃さないと、後々バタバタしない
まとめ
実家をどうするかは、多くの家庭で悩むテーマです。
私たちの場合は、
- 遠距離に住んでいて戻る予定がない
- 管理や維持費の負担を避けたかった
- 親も「売っていい」と言ってくれた
これらの理由から、スムーズに売却を決められました。
ポイントは、
- 「将来住むか住まないか」をまず決めること
- 家族で話し合い記録を残すこと
- 動き出すタイミングを逃さないこと
迷いが少ない人ほど、早めに動くとスムーズですし、次のステップ(片づけ・査定・契約)にも集中できます。
この記事が、あなたの「実家どうする問題」を考えるきっかけになれば幸いです。