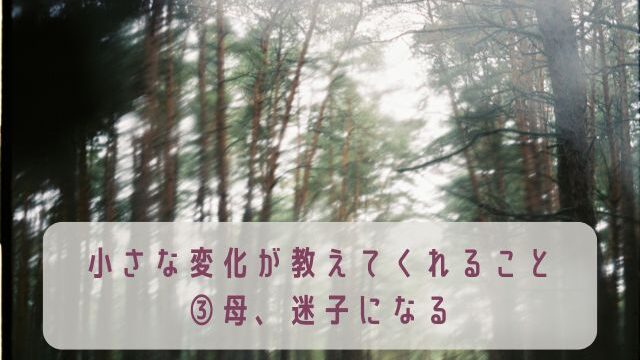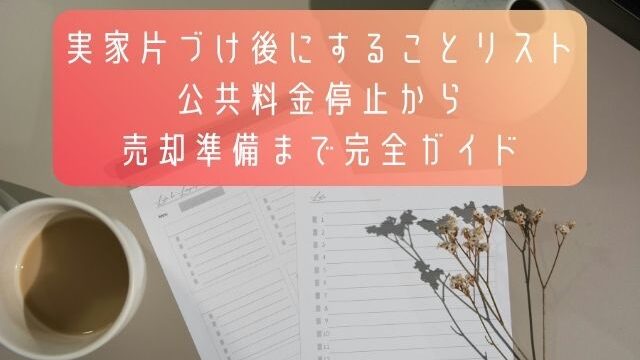まずはここに電話!地域包括支援センターの上手な使い方

高齢の親の言動の変化に不安や疑問を持った時、一番に相談したい場所が「地域包括支援センター」。
その利用の仕方やポイントについて、自身の経験も交えて紹介しています。
「地域包括支援センター」って、どう使えばいいの?
母の様子に不安を感じはじめたころ、ネットや本でいろいろ調べても、専門的すぎてピンとこない…。
そんな中で、知人が教えてくれて出会ったのが「地域包括支援センター」という存在でした。
当時の私は、その「地域包括支援センター」という名前すら知らない人でした。
「そんなところがあるんだ、どこにあるの?どう連絡するの?」「何を話せばいいのかわからない…」――。
そんな疑問や不安を、実際に利用してみた経験をもとに、この記事でわかりやすくお伝えします。

【まずは電話でOK】最初は“心配の気持ち”だけでも大丈夫
地域包括支援センターは、高齢者本人や家族の「困りごと」や「ちょっと気になる」を受け止めてくれる公的窓口です。
私たち姉妹も最初は、「まだ認知症と診断されたわけでもないし、相談していいのかな?」と迷いました。
でも、電話してみて感じたのは、“はっきりしていなくても大丈夫”という安心感でした。
電話口の担当者さんはとても穏やかで、こんなふうに話を引き出してくれました。
- 「どんなときに“ちょっと心配”と感じましたか?」
- 「最近、日常の中で変わった様子はありましたか?」
- 「ご本人やご家族が、困っていることはありますか?」
会話の中で、自分の中のモヤモヤが少しずつ整理されていったのを覚えています。
【相談できること】こんな悩みも、話してOK!
実際に相談してみてわかったのは、想像以上に“幅広いこと”が話せる場所だということ。
たとえば、私たちが話したり、提案されたことはこんな内容でした。
- 「認知症かも?」と思ったときの受診先や検査のすすめ方
- 病院への付き添いや受診のタイミング
- 介護サービスの種類や申請方法(介護認定など)
- ご近所で何かあった場合の連絡体制
- 同居家族(父)へのサポートや心配ごと
「まだ具体的な困りごとはないけれど、少し話を聞いてほしい」という段階でも、真剣に耳を傾けてくれたのが本当にありがたかったです。
【準備しておくと安心】電話前にメモしておきたいこと
電話する前に、以下のようなことをメモしておくと、話しやすく、担当者も状況を把握しやすくなります。
- 高齢者本人の年齢・持病・現在の生活状況(ひとり暮らしか同居かなど)
- 気になっている様子や変化(忘れっぽさ・迷子・服薬ミスなど)
- 家族のサポート体制(誰が、どのくらい関わっているか)
- 相談したい内容(例:病院に行かせたい/介護保険ってどう使う? など)
実際には電話しながら思い出すことも多いので、ざっくり箇条書きでOK。
「これって相談していいのかな?」と思うようなことでも、聞いてみるとヒントをもらえます。
【話した内容は記録に】共有できるノートやアプリを活用
電話で聞いたこと、感じたことは、そのままにせず、メモを残すのがおすすめです。
私たちは、「地域包括に聞いたこと」専用のノートを作り、妹と内容を共有していました。
最近ではLINEのノート機能やGoogleドキュメントを使って、スマホで簡単に共有するのも便利です。
「誰が何を聞いたか」「次のアクションは?」を明確にすることで、遠距離でもチームとして動けるようになります。
【まとめ】迷ったら、まず一度かけてみる
地域包括支援センターは、“何を相談すればいいかわからない”人こそ頼っていい場所です。
親のちょっとした変化に気づいても、「様子を見よう」と先延ばしにしがち。
でも、誰かに話してみることで、自分の不安も整理され、次の一歩が見えてきます。
あの日、思いきって電話してみて本当によかった――。
そう思えるような「はじまりの一歩」になった、地域包括センターとの出会いでした。