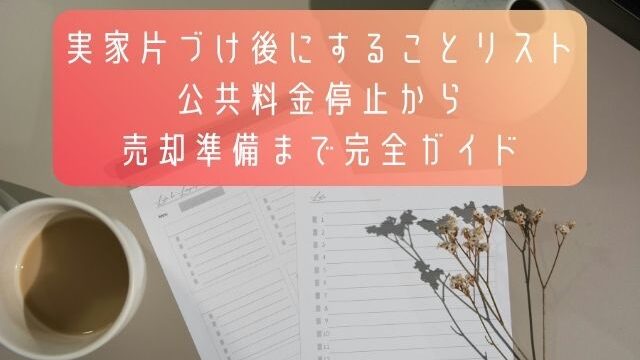はじめての【地域包括センター】 〜どこに相談すればいいの?と思った日

母の様子がなんだかおかしい…でも、どこに相談すれば?
そんな不安を抱えながらたどり着いた「地域包括支援センター」。
誰かに話せることの安心を実感した日を振り返って書いています。
誰かに相談したい。でも、どこに?
不安だったころの気持ち
母の様子が以前と違う!となってから、遠距離住みの私たち姉妹は、最初の2~3年は連絡を取り合いながら、「まだ大丈夫かな」「加齢によるものかも」と思いながら、年に数回、交互に帰省をして見守ってきました。
でも、母の症状が少しづつ、でも帰省のたびに、確実に良くない方へ進んでいる、、
という現実を目の当たりにし、「このままでは、年老いた父と遠距離の姉妹では抱えきれないかも」と感じていきました。
母の生活は、私たちが知らない日々の積み重ねでできているからです。
徐々に、私の中に「このまま様子を見ているだけでいいのかな…?」という不安が募っていきました。
とはいえ、何をどうすればいいかがわからない…。
迷っていた「誰に相談したらいいの?」
認知症のこと、介護のこと、何かを調べようとしても情報は山ほどあって、その分、自分がどこに相談すべきなのかが逆にわからなくなっていました。
「病院に行く?でも、まだ受診するほどでもないような…」
そんな迷いを抱えていたとき、義姉が教えてくれたのが「地域包括支援センター」とケアマネージャーさんの存在でした。
同じころ、妹も職場の方からその情報を得ていました。
今思えば、本屋さんへ行けばいろんな本も出てたと思うけど、当時は焦るばかりでそこの思考回路が抜けていましたね。
地域包括支援センターって、どんなところ?
地域包括センターってなに?
地域包括センターは、市区町村が設置している、高齢者支援のための公的な相談窓口。
介護や医療、認知症、日常生活の不安まで、広くサポートしてくれる場所だそうです。
何よりありがたかったのは、まだ確定診断がない段階でも相談できるということ。
住所によって担当のセンターが決まっているとのことで、ネットで住所を入力して担当センターを調べて、思い切って電話をかけてみました。
実際に電話してみたときのこと
電話口に出てくれた担当の方は、話し方もやわらかく、とても親身になって話を聞いてくれました。
私は、「母が最近ちょっと心配で…」と漠然とした話しかできなかったのですが、
「どんな様子が気になっていますか?」「日常生活で困っていそうなことは?」
と丁寧に質問してくれたことで、私の中でも不安が整理されていくのを感じました。
「お母さまの状態に応じて、こういう選択肢がありますよ」と医療機関の受診や、認知機能のチェック方法なども教えてもらい、ようやく「次にやるべきこと」が見えた瞬間でした。
相談してよかったこと
私はこの電話をきっかけに、「誰にも相談できずにいた」のではなく、「どこに相談すればいいかを知らなかった」だけだったことに気づきました。
地域包括支援センターは、病気の確定診断を待たずに、「ちょっと心配」「誰かと話したい」くらいの段階でも、温かく受け止めてくれます。
あのとき電話して、本当によかったと今でも思います。
- 「私たちだけで抱えなくてもいい」と感じられた
- 地域の支援を知れたことで、次のステップが見えた
- 専門家と話すことで、感情的な不安が整理された
「心配」は、相談していいサイン
私たちはどうしても、「もっと明確な変化が出てから…」と思いがちですが、「ちょっと気になる」や、モヤっとした“心配”の時点で動いてもいい。
むしろ、その早めの相談が、親のこれからを支える第一歩になります。
地域包括センターは、そういう“はじまりの不安”を受け止めてくれる場所でした。
迷ったときこそ、「地域包括支援センター」という選択肢を思い出してみてくださいね。