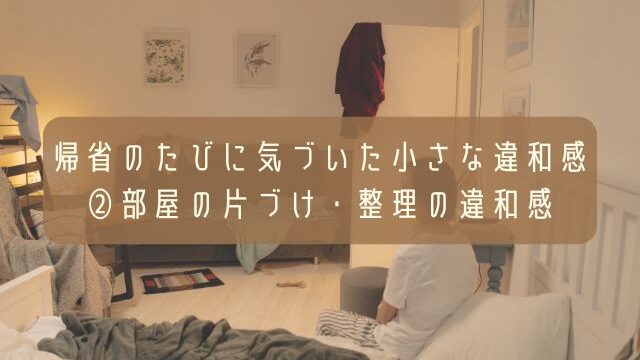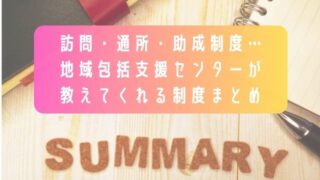確定前でも大丈夫!認知症の不安を相談するタイミングとポイント

高齢の親の様子に「あれっ?」と思っても、専門家に相談するほどじゃないかな、、と思いがち。
この記事では、親の今までと違う言動や認知症かも?の不安を相談するタイミングやポイントについて書いています。

迷いながらも「まだいいかな」と先延ばしに
「最近ちょっとおかしい気がするけど、年のせいかも…」
認知症の初期症状かも?と思いながらも、「まだ病院に行くほどじゃない」「本人に言うのも気が引ける」と、私たち姉妹はしばらく様子を見る日々が続きました。
今思えば、早く相談していれば…と思う場面もたくさん。
今回は、“確定診断前でも相談していいタイミングとポイント”を、私たちの経験をもとにまとめます。
相談のタイミング:初期兆候、日常の“ちょっとしたサイン”
認知症は、はっきりした症状が出るまでに時間がかかることが多く、最初は「あれ?」という違和感程度のことが多いです。
でも、その“ちょっとしたサイン”が、相談のきっかけになります。
私たち姉妹が気づいた変化の一例は下記のような感じ。
- 曜日や日付をよく間違えるようになった
- 冷蔵庫の中に同じ食品がいくつも入っていた
- 洗濯物が溜まっていても気にしていない様子
- おしゃれだったのに服装が乱れてきた
- 予定をよく忘れるようになった
- 迷子になった(と後から親族から聞いた)
これらは、“確信が持てないけど不安な変化”。
そんなときこそ、地域包括支援センターなどに相談する絶好のタイミングです。
確定診断がなくても、専門職の方が状況を聞き取って、必要なサポートや次のステップを一緒に考えてくれます。

相談時に聞いておきたいこと/ポイント
相談時には、ただ状況を話すだけでなく、今後の見通しを立てるヒントをもらうことも大切です。
私が地域包括支援センターに電話したとき、以下のようなことを質問しておいてよかったと感じました。
- 認知機能チェックはどこで受けられる?
- 地元で信頼できる医療機関はある?
- 今すぐ診断を受けなくても、事前にしておく準備は?
- ケアマネージャーさんにいつから関わってもらえるの?
何を聞けばいいかわからなくても、担当の方がやさしく導いてくれるので安心です。
家族で共有するコツ:情報共有ノートの作り方
遠距離でサポートしていると、家族間の情報共有がとても大切になります。
私たち姉妹は、簡単な“共有ノート”を作って、母の変化や気になったことをメモし合うようにしました。
- GoogleドキュメントやLINEノートなどで共有
- 帰省時の観察記録、話した内容を簡潔に記録
- 「ちょっと気になったこと」でもメモ
- 気になることに★マークをつけておくと振り返りやすい
書き方に正解はありませんが、「なんとなく気になること」を記録することで、複数の家族が同じ視点で親をを見守ることができるようになりました。

【まとめ】
「まだ大丈夫かも」と思っても、その“気づき”こそが第一歩。
確定診断がなくても、誰かに相談することで気持ちが整理され、次にどう動くかが見えてきます。
地域包括支援センターなど、早めに相談できる場所を知っておくことが、家族にとっても大きな安心になります。